2025.10.28
AIってすごい
みなさんAIは活用していますか?
私は最近めちゃくちゃお世話になっています。
気になることだったり、アイデアをだしてもらったり…いろんな活用方法がありますよね!
私も最近[Notion]という文章生成AIを使っています!!
私の趣味の一つが読書をすることなのですが、最近ビビッと来るいい本に巡り合えないな…と本屋さんを渡り歩いていた時、ふと思いつきました。
「そうだ!AIに小説を書いてもらおう!」
と、さっそくNotion先生に「三島由紀夫のような作風の短編小説を作成して」とお願いすると素敵な短編小説をたくさん生成してくれました。
しっかり三島由紀夫らしい伝統と破滅の緊張、彫琢された比喩、端正な文体で生成してくれました。
こんなのが読みたい!を叶えてくれるAIってホントすごい!けど恐ろしい…
Notion先生に生成してもらった短編小説の中で特に好きなお話を下に続けます。
少し長いので時間があるときにぜひ読んでください(o^―^o)
硝子の朝
夜明けの直前、海はまだ鉛色の幕のように閉ざされ、波の呼吸だけがゆっくりと浜を撫でていた。誠は砂に素足を埋め、手の甲で自分の脈を確かめる。規則的な跳躍は、訓練を積んだ兵の行進のように正確だった。彼は薄く笑い、潮風の塩を舌で味わう。塩は、血に似た味をしている。
丘の上には、神社の小さな社があり、鳥居は夜の影をまだわずかにまとっている。誠は毎朝そこで礼をする。礼は身を整えるためであり、体を整えることは心を整えることに等しい。彼にとって意志とは筋肉の別名であり、美しさとは秩序の別名だった。
「今日で最後だ」と彼は心の内で言う。その言葉は、砂浜の冷気のように淡々としていた。彼は黒い木箱を抱えている。箱には祖父の遺した脇差が納められていた。祖父は戦の残響の中で老い、静かに死んだが、その眼差しは最後まで遠い太陽を見上げる兵のそれであったと、父は語った。
誠は浜に背を向け、石段をのぼる。石の肌は夜露で湿り、踏むたびに小さな音を漏らす。社の前に立つと、彼は箱を開き、白布に包まれた刃を取り出した。朝の欠片のように、鋼はまだ光を持たない。彼は布で丁寧に拭い、息をかけた。温度が伝わると、刃は薄く、まるで自分の意識に応ずるように微光を帯びる。
社は古びているが、釘一本にも怠りはない。彼は賽銭を投じ、二度打ち、深く礼をした。願うことはない。願いはいつも甘く、甘さは心を弛緩させる。彼が捧げるのは祈りではなく、姿勢だった。
ふと、背後から足音がした。振り向くと、白いワンピースの女が立っていた。髪は肩で切り揃えられ、眼は夜の残響を湛えている。
「朝は、あなたのものですか」と女が言う。
「誰のものでもない」と誠は答えた。「ただ、身を置く場所が要る」
「身を置くために刃が要るのですね」
彼は脇差を見下ろす。「刃は鏡です。曇りを映すための」
女は社の横の手水舎で、指先を濡らして額に当てた。「昔、ここで誰かが待っていました。潮の匂いを聞きながら」
「潮の匂いは聞こえない」
女は笑った。「あなたには。けれど、私は音で世界を覚えます。波は鐘の音に似て、風は和紙を裂く音に似て、朝は硝子の割れる音に似ています」
誠はその言葉を内側で反芻した。硝子の朝。壊れやすさと透明さが同居する刻。彼は刃を白布に戻し、箱を閉めた。「あなたは何を待つ」
「誰かが剥き出しの顔で嘘をつく瞬間」
「嘘は顔を隠すためにある」
「ええ。でも、嘘にも形があります。きれいな嘘は、触れると切れます」
沈黙が二人の間を流れた。鳥の一声が、夜と朝の境を縫い合わせる針のように空へ走った。誠は石段を降り始め、女も並んだ。二人の影は長く伸び、やがて重なり、ほどけた。
浜に戻ると、空の端が薄く朱を宿している。女は足もとで砂を掬い、掌からこぼした。「私の父は漁師でした。網を上げると、魚よりも先に、切れた糸や錆びた針が上がる日がありました。父はそういう日を、運が良いと言いました」
「残骸が兆すと」
「ええ。壊れたものが次を呼ぶから」
誠は脇差の箱を砂に置き、上衣を脱いだ。皮膚は朝の冷気を細かく刻んだ紙のように震え、彼はその震えを抑えるのではなく、一定の律動として迎え入れる。彼は身体を緊張させ、片膝を沈め、両掌を砂に押し付ける。砂は受け入れ、わずかに沈み、彼の体重の形を覚えた。
「今日で最後だと言いましたね」と女が言った。
「言っていない」
「あなたの背中が言いました」
誠は立ち上がる。「終わりは、形を与えるためにある」
「では、あなたは何に形を与えるのですか」
彼は答えず、海へ歩き出した。波が足首を打ち、膝を、腿を、腰を冷やす。体温は、内側から剥がれてゆく皮のように離れていく。彼は胸まで水に入り、振り返った。女は砂の上で、まるで見送る儀式の役目を自覚しているように、ただ立っている。
誠は深く息を吸い、肺の隅まで満たし、そして吐いた。呼吸は刃の手入れと同じで、怠れば鈍る。彼は二歩、三歩、さらに沖へ。波の下で、彼は目を閉じた。暗闇には形がない。形は光の副産物だ。彼は手で水を掻き、耳の中の世界が泡立つ音を聴く。心拍はゆるやかに、しかし確実に、潮の隊列へ歩調を合わせる。
そのとき、彼はふいに理解した。自分が欲してきたのは終わりではない。形でもない。――不可逆であることだった。やり直せない一度きりの選択。不可逆は、世界に最も近い真実だからだ。
彼は岸へ戻った。身体から水が滴るたび、細い銀の糸が砂に刺さり、消えた。女は黙って彼を見ている。誠は箱を開け、白布を解いた。刃は朝陽を迎え、今度ははっきりと光った。彼は刃を海にかざし、波打ち際の小石の上にゆっくりと置いた。
「終わりは置いていく」と彼は言った。「不可逆は持っていく」
女は小さく頷いた。「では、あなたはどこへ行くのです」
「形のないところへ」
「そこでも、朝は割れますか」
彼はわずかに笑み、空を見上げた。朱は金に変わり、金は白へとほどける。鳥の声が増え、遠くで誰かが砂を踏む音がした。世界は、整然と動き始める。
誠は濡れた衣を肩にかけ、社の方角に一礼し、背を向けた。女は砂に片膝をつき、脇差に指を伸ばす。けれど触れず、指先だけでその輪郭をなぞる。硝子の朝が割れる音がした。二人はそれぞれの不可逆を、誰にも告げずに受け取った。
背中に太陽の重みが宿る。誠は歩いた。歩みは静かで、しかし内側では、針のように鋭い音がひとつずつ鳴っていた。彼はその音を、自分のものとして数えた。数えることは、裏切らない。やがて音は数え切れなくなり、ただの静けさへと戻るだろう。そのとき、彼はまた、どこかの朝を割るに違いない。
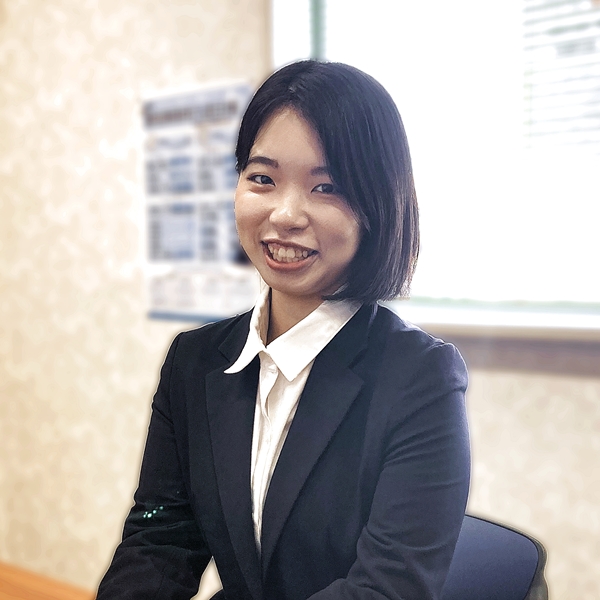
この記事を書いた人
苫米地美有先生
静岡県の海の近くで育ち、主に国語を専門に学ぶ。愛嬌満点、やる気も満点!楽しく面白くをモットーに、勉強が苦手でも嫌いにならないように学んでいく手助けをします。お散歩と駄菓子が大好きで「タラタラしてんじゃねーよ」を心から愛する。
▶この講師のブログへ